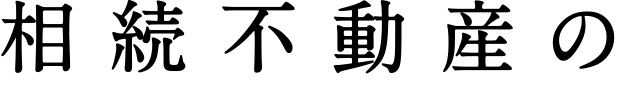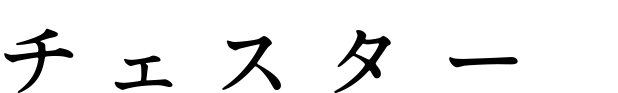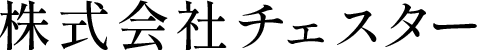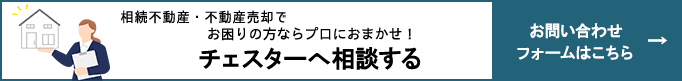家購入にかかわるあらゆる費用とその節約法を徹底解説

「家の購入を考えているけれど、費用はどれくらいかかるんだろう……」
「お金に余裕がないんだけど、費用を節約して家を購入する方法ってないのかな……」
と家の購入にかかる費用について不安に感じている方も多いのではないでしょうか?
確かに家の購入には実際に多くの費用がかかります。
しかし、きちんと事前に費用の内訳を把握しておけば、どの部分を節約できるか事前準備することが可能です。
購入する物件について迷っている方は「TERASS」という不動産エージェントでプロに相談してみるのがおすすめですよ。
⇒不動産売買|不動産売却・不動産購入で押さえておくべきポイントまとめ
1.家の購入にかかる費用を抑えるコツ
家の購入には最大の出費となる住宅ローン以外にも多くの費用がかかります。
少しでも節約するためには、「どんな費用がかかるのか」「どの費用なら節約できるのか」を事前に確認しておく必要があるでしょう。
家の購入にかかる諸経費とは契約の手続きや登記などにかかるお金で、マンションの場合は建物費用の5%、建売で6%、注文住宅は10%と考えるのが一般的な目安です。
家を建てたり住宅ローンを利用したりするときに必要な諸経費には以下のものがあります。
- ・融資事務手数料
- ・保証料
- ・つなぎ融資費用
- ・収入印紙代
- ・登記関係費用
- ・火災保険料
- ・仲介手数料
このなかで、コストダウンできないものは、収入印紙代のみで、他の諸経費は時間を使ったり工夫をすればコストダウンができる諸経費になります。
ただ、地鎮祭などの費用は「縁起ものなので値切らない」といったメリハリのある資金計画をしたいものです。
⇒家の購入の流れと費用の発生タイミングを解説!いついくらかかる?
2.家の購入にかかる費用の詳細
住宅を購入すると、家本体の価格だけではなく、別途費用が必要になります。
家の購入の際には、外構工事であったり、保険や税金であったりと、実に様々な費用がかかります。
家づくりでは、建築に関係する本体工事費と付帯工事費を合わせて、建築工事費といい、その他に諸費用がかかります。
諸費用は建築工事費の5%から7%が相場だと言われている通り、決して安価ではありません。
条件によってかかる費用が変わってきますし、追加でプランを変更したくなった時や、想定外の事態が起きてしまった時のために、できれば10%ほどの資金を確保しておくのが望ましいです。
一般的に諸費用といわれているものはどのようなものがあるのかご紹介します。
- ・ローン関連の、事務手数料や抵当権設定費用
- ・仲介手数料や売買契約書に貼るための印紙税
- ・土地や建物にかかる登記代
- ・新居にかかる火災・地震保険料
- ・引越し代・家具家電購入費など
- ・不動産取得税
このなかでも、登記費用や税金は物件価格や借入金によって金額が決まっています。
家具家電の購入費などは、家計の状況を見ながら、旧宅で使っていたものや、追々買っても構わないものなどの選別ができて、費用の調節が可能なものが多いです。
住宅購入の際には、頭金や手付金とは別で、住宅引き渡しの前に支払うこのような「諸費用」を念頭に置く必要があります。
というのも、費用は基本的に住宅ローンの契約(入金)前に現金で用意しておかなければいけないため、頭金とは別で用意しておかなければならないからです。
諸費用は、すべて合わせると数十万円から100万円単位になります。
「そんなに手持ち資金がない……」という方は、諸費用分を1年ほど貯金するなどして住宅購入を検討しましょう。
どうしても今すぐ購入したいという場合、「諸費用ローン」が組める銀行もあります。しかし、契約に際して住宅ローンとは別に手数料が取られることや、住宅ローンより金利が高く設定してあることなどのデメリットもあります。諸費用ローンについて詳しくは「3.家購入時の諸費用についてはローンを組むこともできる」をご覧ください。
諸費用分はできるだけ現金で用意するためにも、それぞれどのくらいの費用がかかるのかを事前に確認しておきましょう。
まずは住宅ローンにかかる諸費用(金融機関に払うもの)について見ていきたいと思います。
2-1.金融機関に関わる費用
住宅ローンの諸経費のなかには、金融機関に払うもの、保証会社に払うもの、保険料として将来の自分自身に払うものがあります。
いずれも住宅ローンの借り入れに不可欠な費用です。
住宅購入の際に予算オーバーになってしまい、諸経費を削ることにならないように、当初の資金計画から諸費用を差し引いた価格で、建築費の予算計画を立てていきましょう。
しかし、諸費用は注文住宅でいえば住宅購入総額全体のうちで、建物費用の10%に当たる大きな割合を占めます。
費用削減の努力をするのとしないのでは資金計画に大きな差があるといえます。
住宅ローンに関わる諸費用は主に、事務手数料と保証料、さらに団体信用生命保険料です。
事務手数料と保証料は金融機関と保証会社に支払う経費ですが、団体信用生命保険料は自分自身のために支払う保険料になります。
事務手数料、保証料は共に定額制と定率制があり、金融機関によって、内容や金額は違ってきます。
メガバンク・地銀・ネット銀行を例にかかる費用をシミュレーションで比較してみましょう。
借入額2500万円・35年返済・消費税は10%の場合
◎メガバンク
事務手数料は33,000円で、保証料は金利0.2%上乗せ、もしくは一括前払いで約52万円でした。
◎地銀
銀行事務手数料22,000円と保証会社事務手数料が33,000円で、保証料は金利0.2%~0.4%上乗せ、もしくは一括前払いで約52万円でした。
◎ネット銀行A
事務手数料は借入れ金額の2%+消費税で55万円で、保証料は無料でした。この銀行は、全疾病保障も無料で付けられるそうです。
◎ネット銀行B
借入プランごとに事務手数料が変わり、5万5,000円・11万円・16万5,000円と分かれています。
保証料は、こちらも無料でしたし、プランにより介護特約も無料でした。
事務手数料と保証料は別々の諸経費ですが、これをセットと考えると諸費用の総額が見えやすくなってきます。
メガバンクは事務手数料は3万円+消費税なので低く見えます。
しかし、保証料は金利0.2%上乗せ、もしくは一括前払いで約52万円となっていて、保証料無料のネット銀行と比較すると高額です。事務手数料を合わせた金額は、ネット銀行Aとおおむね同額になります。
ただでさえ、住宅購入は大きなお金がかかるため、保証料や事務手数料は安い方がいいと考えてしまいがちです。
ですが、安い高いよりも、継続して返済ができるのかということを考えることが大事です。
一括前払いの方が安いからと、一括で払ったら現金が足りなくなり、結局、諸経費のローンを組んでしまったとなっては意味がありません。
また、保証料が無料でも金利が高いという可能性もあります。
どう返済していくかを念頭に入れて最終決断をしましょう。
さて、家の購入にかかる費用のうち最もコストダウンの工夫がしやすいものは、融資事務手数料と保証料ですが、どのように工夫すればよいのでしょうか。
それぞれについて順を追って確認していきましょう。
2-1-1.融資手数料
融資手数料は事務手数料として記載されていることもあります。
住宅ローンを借りる際に必ず発生するこの融資事務手数料は、金融機関ごとに価格の設定が違うので、これが安い金融機関を選ぶことで、諸費用全体を削減することができます。
フラット35など、内容は同じローン商品でも、取り扱う金融機関によって融資手数料が異なります。
融資事務手数料には一括で払う定額型と、借入額をベースに計算する定率型の2種類があります。
3万円~10万円程度の定額で設定しているところもあれば、融資額の2%など、定率で設定しているところもあります。
定率で設定している場合、融資額によって「手数料」が大きく跳ね上がるので注意してください。0.75%程度であれば、3,000万円の融資に対して22万5千円ほどの手数料となります。2%も設定してあった場合は、60万円もの融資手数料がかかることになるのですね。
しかし、「融資手数料を高く設定している分、金利が安い」といったケースも大いにあります。
13年以上借入期間がある場合、「定率型」を選んだ方が、総支払額が少ないケースが多いです。
ただし、銀行や金利によって変わりますので、詳しくは銀行の担当者に計算をお願いしてみると良いでしょう。
手数料の金額だけにこだわるのではなく、金利とのバランスを考えて住宅ローンを選びたいですね。
住宅ローンを選ぶ際は、「融資手数料+総返済額」を計算して、総額いくら支払うのかに注目すると良いでしょう。
2-1-2.保証料
保証料は保証会社に支払う費用で、借り入れをするときに保証人を立てる代わりに保証会社にお金を払って保証してもらうためのものです。
銀行の住宅ローン商品は多くの場合、保証会社の保証をつけることが、住宅ローンを融資する際の条件になっています。
ローン保証とは、ローン返済が滞った際に、保証会社が銀行への返済を立て替える仕組みです。
ローン保証は、銀行側にとって確実にローンの回収ができると担保されているメリットがあります。
しかし、返済者からすると、返済が滞ってしまった際の救済として機能するわけではなく、返済先が銀行から保証会社に変わるだけです。
万が一、返済が滞ってしまった時には、保証会社が代わりに返済をして、以降は保証会社に返済をしていくことになります。
ローン保証料は借入金額と返済期間によって決まります。
返済期間が長期になるほど高くなるため、なるべく「返済期間」を短くすることでローン保証料を節約することができます。
借り手が住宅ローンの返済ができなくなった場合に備えて、保証会社に保証を依頼するために支払う保証料も、融資の契約の時に全額支払う一括方式(前払い)と、毎月の返済額に分割して支払う外枠方式(後払い)の2種類があります。ローン契約時に諸費用の一つとして一括払いする方式と、金利に上乗せして毎月支払う方式(融資金利+0.2~0.3%)があるということです。
一括支払いの場合、諸費用として最初に支払うため、手持ち資金が少ない人にとっては大きな負担になります。
最近は、金利に上乗せして返済額と一緒に毎月支払っていくプランを提供している銀行も多いです。
ただし手元に現金がなければ、毎月の返済額から差し引かれてしまう後払いしか選択肢はなくなってしまいます。
その場合、金利が上乗せされて割高になってしまうので、一括で支払える現金があるのでしたら自分の借り入れの条件に合わせて、安い方を選ぶと良いでしょう。
融資事務手数料や保証料が安い金融機関は、その他の費用や金利が高い場合があるので、差し引きいくら払うことになるのかを計算することが重要です。
2-1-3.印紙税
そして、忘れがちな費用の一つが印紙税です。
ネット銀行などでは、ペーパーレスにしているところは印紙が必要ありませんが、紙で契約をするときには、印紙代が2万円以上かかります。
住宅ローンの契約に際して発行される「金銭消費貸借契約書」へ印紙を貼付します。
2-1-4.つなぎ融資
状況によってはつなぎ融資が必要となる方もいらっしゃるでしょう。
つなぎ融資は日ごとに利息が発生するので、借り入れを一日でも短くするのが有効です。
といっても、工事期間がどの程度の長さになるかわからないので、契約時に決済の時期を少し遅らせておくといいでしょう。
土地を購入してすぐに着工できれば、融資の期間が短くなり、利息が低くなります。
手元に土地代分の現金があれば、つなぎ融資は不要になるのでベストです。
2-1-5.団体信用生命保険
団体信用生命保険は保険金受取人を銀行にしてローン契約者にかける生命保険です。
住宅ローンの契約者(返済者)が死亡または高度障害状態になったときに、銀行等に保険金が支払われます。
住宅ローンの残債は、保険金で相殺される仕組みです。
住宅ローンは残らず、家は残るので、加入することで万が一の時にも、家族を路頭に迷わせることもなく安心して住宅ローンが組めます。
ローンを借り入れた人に万が一があった時に、ローン残高に相当する保険金が支払われて、住宅ローンが完済されます。
保険料は借入額や返済年数に応じて別途支払うタイプと、金利に上乗せするタイプがあります。
団信保険料は金利込みにしているプランが主流です。
ただし、疾病保障付きの団信の場合は、保障内容により0.1~0.3%程度のローン金利が保険料分として上乗せ徴収されるものが一般的です。
預金が少ないご家庭、世帯主にしか収入がないのでその人に何かあったらリスクが大きいというケースなど、必要がある場合は保障がたくさんある保険に加入すると良いでしょう。
保険料の負担が大きいと感じたら、保障内容を削るのではなく、物件の建築費を見直すのが望ましいと考えられます。
銀行は一般的に団信に加入できない人には融資しませんので、健康でないと銀行から借入れができません。
他に加入している生命保険があるなら、保障内容や支払われる保険金とのバランスをみて加入すべきか否かを判断しましょう。
家族がいるばあい、万が一のときを考えた十分な備えは必要です。
2-2.建物や土地の購入に関わる費用
金融機関に関わるお金の概要を整理したところで、今度は建物の建築や土地の購入に関わるお金を見ていきましょう。
2-2-1.消費税
まず、住宅購入の際にかかる税金の詳細について見ていきましょう。
住宅を購入する際は、消費税を含めさまざまな税金がかかります。
普段、買い物をしている商品と同じように住宅の購入にも10%の消費税がかかります。
マイホームは非常に高額ですので、消費税が100万円以上となってしまうことは決して珍しくありません。
不動産取引の場合、消費税がかかるのは建物価格だけで、土地代には消費税はかかりません。
そのため、新築住宅を購入する際や、家の新築をする際、新築マンションを購入する際などは、建物分の価格に消費税が課税されます。
例えば、建売住宅やマンションを購入した場合、価格が5,000万円(建物分2,000万円、土地分3,000万円)だとすれば、建物分の2,000万円のみに消費税が課税されます。
建物価格は2,000万円×10%で税込2,200万円となります。
消費税は他にも、新築や増改築の際の建築工事費や設計料、リフォーム代、諸費用の仲介手数料や司法書士の報酬、ローン手数料などにもかかります。
ただし、個人間でのやり取りの場合は消費税はかからないため、個人が売主の中古住宅を購入する場合は、建物にも土地にも消費税は課税されません。
住宅を購入する際は、消費税を考えずに資金計画を立ててしまうと、大きく予算をオーバーしてしまい、妥協せざるを得ないことが多数出てくる可能性があります。
2-2-2.印紙税
次に印紙税ですが、これは売買契約書と工事請負契約書を作成するための印紙代です。
印紙税は、契約書に印紙を貼付して支払う税金です。
住宅購入の際は「売買契約書」に印紙を貼る必要があります。
注文住宅であれば「工事請負契約書」に貼付します。
土地の購入から行い、注文住宅を建てる場合は土地の「売買契約書」と、建築費の「工事請負契約書」に印紙を貼る必要があります。
| 契約書の記載金額・契約書に貼付する印紙の価格 | |
|---|---|
| 100万円を超え500万円以下 | 2千円(1千円) |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円(5千円) |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円(1万円) |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円(3万円) |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円(6万円) |
| 契約書の記載金額・契約書に貼付する印紙の価格 | |
|---|---|
| 300万円を超え500万円以下 | 2千円(1千円) |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円(5千円) |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円(1万円) |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円(3万円) |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円(6万円) |
税なので、減額することはできません。
⇒不動産の売却に伴う売買契約書の印紙税について
2-2-3.登記免許税・司法書士報酬
家を購入すると登録免許税という、不動産取得で登記した時にかかる税金を国に支払わないといけません。
住宅を購入する際は、その住宅が誰のものかを明確にするために「登記」を行います。
自分が購入したということを証明して、土地や建物の名義を登録する手続きが必要です。
登録免許税の計算については次のようになります。
- ・土地や建物の固定資産税評価額をもとに計算する
・住宅ローンを組む(抵当権を設定する)場合は、債権額(借入額)をもとに計算する
・新築住宅で固定資産税評価額が確定していない場合は、法務局が認定する課税標準額に税率をかける
税率については次のようになっています。
| 所有権移転登記 | 土地を購入した場合 | 2.0%(令和8年3月31日までに登記をする場合は軽減税率1.5%) |
|---|---|---|
| 中古の建物を購入した場合 | 2.0%(令和9年3月31日までに取得する場合は軽減税率0.3%) | |
| 抵当権設定登記 | 0.4%(令和9年3月31日までに新築・取得する場合は軽減税率0.1%) | |
| 所有権保存登記(新築の建物を購入した場合) | 0.4%(令和9年3月31日までに新築する場合は軽減税率0.15%) | |
(建物の所有権移転登記、抵当権設定登記、所有権保存登記の軽減税率の適用は、床面積が50㎡以上であるなど一定の要件を満たす必要があります。)
登録免許税は上の税率を元に次のように計算できます。
- 「もとにする金額(評価額や債権額)」×「税率」=登録免許税
- 土地の登録免許税+建物の登録免許税+抵当権の登録免許税=支払う登録免許税の合計額
新築よりも中古の方が物件価格が安かったとしても、費用が高くなることで、新築と中古の費用差がほとんどなくなってしまうことがあります。
原則、登記は専門的な知識がないと大変面倒な手続きになるので、住宅を購入して登記する場合には、司法書士に依頼することになります。
すると、登録免許税とあわせて、「司法書士報酬」を支払う必要があります。
司法書士報酬は、地域により相場が違い、また同じ地域でも事務所やケースによって大きく金額が異なります。
家を建てた場合は「所有権保存登記」を行います。
この報酬の相場は全国平均で約2万円です。
建売住宅や中古住宅、マンションを購入する場合は「所有権移転登記」を行います。
この場合の司法書士報酬の相場は、全国平均で5万円ほどです。
また、住宅ローンを組んで、住宅購入や住宅建築をする場合、物件に「抵当権」を設定するために「抵当権設定登記」が必要になります。
抵当権の設定に関する報酬の相場は、全国平均で3万5千円程度となっています。
登記に関わる費用についても、コストダウンできるポイントと減額不可の項目があります。
登記関係費用は司法書士に支払う諸経費です。
各登記1回で8万円から20万円と幅広く、安く請け負ってくれる司法書士を探すのが減額のポイントです。
司法書士は金融機関から担当者を指定されることが多いのですが、指定がなければ報酬の安い事務所を自分で探して、金融機関にそちらに委託してもいいかという相談をするのも効果的です。
⇒相続登記に関わる費用もろもろ
2-2-4.物件検査手数料
さらに物件検査手数料という、自分の住宅が国の建築基準に違反していないかを調査するための費用がかかる場合があります。
2-3.火災保険・地震保険
住宅ローン契約をする場合、「火災保険」への加入は必須ともいわれます。
過去にはローンの借入期間分を一括で支払うケースがほとんどでしたが、現在は火災保険の契約期間は最長で5年となっています。しかし、更新のつど保険料を支払うので、長期的には大きな負担となる場合もあります。
住宅ローンを組んで住宅購入・住宅建築をする場合、火災保険の加入はほとんど必須といっても良いでしょう。
ただし、どの保険会社のどんなプランを契約するかを工夫すれば、保険料を安く抑えることができます。
近年、ネットで契約するタイプの火災保険が登場していて、掛け金が安く設定されているケースもあります。
万が一火災などで家が損傷・喪失した場合、銀行が優先的に保険金を受け取る「質権」を設定する場合もあります。
この場合、銀行が指定した火災保険を契約する必要があるかもしれません。
地震保険は、任意で加入の有無を決められますが、東日本大震災以降、火災保険と併せて加入する人が増えています。
地震・噴火・津波による被害は、通常の火災保険ではカバーされません。
もっというと、地震が原因で起きた火災の場合も、地震保険からでないと保険金は受け取れません。
そのため、地震保険は、火災保険のオプション的な位置づけで契約しておくことがおすすめです。
2-4.一戸建てを新築するときにかかる費用
一戸建てだと水道分担金や建物調査費用、地鎮祭費用や上棟費用など、特有の諸費用がかかります。
いずれも安い金額ではないため、事前に把握をして十分な自己資金を準備しておく必要があります。
「知らなかった」「後で知った」では非常に困ってしまいますので、これらの諸費用がかかることを把握し、マイホーム購入の際は事前に金額を確認してください。
水道分担金とは、マイホームに水道を引くために自治体に支払う費用のことで10万円〜30万円程度かかってきます。
また、注文住宅の場合は、土地の地盤や建物の安全性を確かめてもらうために、検査機関に調査を依頼することがあります。
この調査にも費用がかかり、建物調査であれば40万円〜70万円程度、高い場合は100万円程度もかかります。
さらに、マイホームの工事前におこなう地鎮祭は5万円程度、上棟式の際にかかる祝儀や料理などに10万円〜30万円必要です。
物件価格以外に「どんな費用がどれくらいかかるか」を事前に把握しておかないと、購入計画が狂ってしまう可能性が出てきます。
物件価格に加え、事務手数料などの諸費用も考慮したうえで、物件を比較・判断するようにしてください。
2-5.中古物件を購入するときにかかる仲介手数料
新築と違って、中古物件を購入する際は不動産仲介業者に仲介手数料を支払う必要が出てきます。
中古住宅や中古マンションなど、中古でマイホームを購入する際は、新築に比べ2〜3割は物件価格が安いといわれています。
しかし、気をつけなければならないのが、中古の場合は諸費用が高くなる傾向があることです。
中古の場合、新築のマイホームを購入する際にはかからない仲介手数料が発生してしまうため、諸費用が高くなってしまいます。
中古物件を個人間で売買するケースは少なく、一般的に売主も買主も不動産仲介業者を利用して中古物件の売買をします。
その場合は、「仲介」となるため、物件の売買が成立したら業者に対して仲介手数料を支払う必要が出てきます。
物件価格にもよりますが、手数料が100万円を超えることもあるため、事前に把握をしておかないと資金計画が狂ってしまいます。
新築ではなく、中古物件を検討している方は、手数料について必ず事前に確認しておきましょう。
仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限金額が定められています。
- 「(売買金額×3%+6万円)+消費税」(400万円超の場合)
という式で簡易的に上限額が計算できます。
仲介手数料の料率については、下記のように売買価格によって異なりますので注意してください。
| 売買価格 | 仲介手数料の料率 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5% |
| 200万円超400万円以下の部分 | 4% |
| 400万円超の部分 | 3% |
2-6.その他の諸費用
高低差がある土地や、道路から離れている土地は、ガスや水道の引き込み費用が高くなります。
家を建てられない地盤の弱い土地ならば、地盤改良工事の費用がかかりますし、それを調べるためにも地盤調査費がかかります。
地盤改良費はその地盤の強度や建てる家の構法によっても変わるので、一概に値段はいえません。
安い土地を買ったとしても、調査の結果土地が家を建てられる状態でなかったら、数十万円、ないし数百万円の追加費用を払って整備しないといけません。
逆に言ってしまうと、少し高かったとしても環境の整備された住宅地を購入した場合、別途費用は相場より安くなることも考えられます。
引き込んだ水道管などを家の内部に引き入れるのにも、敷き設工事といって引き込み費用とは別にかかってきます。
駐車場や玄関までのアプローチにこだわる人は外構費用が高くなりがちですし、庭にこだわる人は、造園工事が高額になる恐れがあります。
最近では太陽光発電も人気ですから、特殊設備工事費などもかかってくるかもしれません。
日常生活に欠かせない空調設備工事や、照明器具工事、カーテン工事もあります。
家を設計する時に設計事務所や建築家に依頼した場合は設計料も必要になります。
住宅会社が提案する建築工事費に、どの別途工事まで含まれているかを確認することも重要かもしれません。
また、家を買うと、引越しはつきものです。
必要資金として見積っておくと安心です。
- 引っ越し費用の相場……一戸建て(新築)14.1万円~中古住宅45.5万円程度
| 住宅建築・購入後おおむね1年以内に購入した耐久消費財(新生活費用)の平均的な額 | |
|---|---|
| 中古住宅 | 45.5万円程度 |
| 一戸建て(新築) | 155.1万円 |
新築一戸建てで額が大きくなる理由としては、新しい住まいへ引っ越すタイミングで家電を新調する方が多い点や、カーテンや照明など、以前のすまいと違う型を用意しなければいけない点などがあります。
エアコンなどは、大型家電ですが、各部屋に必要になるなど、まとめて大きな額が出ていきます。
その他にも、家を解体して建て直す人は、仮住まいの費用が発生しますし、新居で新しい家具や家電を設置する場合は、家具家電の購入費もかかります。
金融機関に支払う諸費用と比べると融通の利く内容もありますが、想定外の事態が起こらないとも限りませんので、それに備えての予備費用も確保するに越したことはありません。
建物本体に関わる費用についても、よく耳にする坪単価いくら!とか、何とか万円の家!と謳っている広告は、ほとんどが本体工事費の値段といっても過言ではありません。
本体工事費は、購入費用の75%から80%が相場です。
仮に2000万円の家という建築会社の家があるとして、この価格が本体工事費を指していた場合には、総金額は2500万円から2700万円になり、500万円から700万円も多く払うことになってしまいます。
本体工事費とはその名の通り、建物本体だけの値段です。
それとは別に、ガスや水道などのライフラインの工事や、駐車場や庭などの外構工事などがあり、総費用の15%から20%を見込みます。
これを付帯工事費といい、家を建てる土地などの条件で金額が大きく変わってきてしまいます。
元々家が建っていたのなら、それを壊すのに解体工事費がかかります。
一つ一つに対策をすることで、最終的に大きな諸費用の削減につながります。
工事の他にも、火災保険や地震保険などの保険金も発生します。
土地や建物以外には、地鎮祭や上棟式の費用も予定外に発生する可能性がある費用の一つです。
理想の家づくりは、本体工事費だけではなく、付帯工事費、諸経費など様々な費用がかかることが分かっていただけたかと思います。
イメージ通りの家を建てるためには、建物だけではなく、それ以外のどこに、どれだけの費用がかかるのかを想定して、注意して資金計画を立てるようにしましょう。
3.家購入時の諸費用についてはローンを組むこともできる
マイホームを購入したくなるタイミングは人それぞれで、必ずしも自己資金が準備できているとは限らないですよね。
マイホームを購入する際は、物件価格だけでなく諸費用も必要となるため、一般的にはある程度の自己資金を準備しておく必要があるといわれています。
ここから、諸費用ローンの特徴や注意点についてご紹介していきましょう。
マイホームを購入する際は、印紙税や登録免許税、不動産取得税、ローン保証料、事務手数料、火災保険料、地震保険料、団体信用生命保険料、仲介手数料(中古物件)などの諸費用が物件価格の3%〜10%程度かかります。
そのため、仮に、物件価格が3,000万円だとすれば、90万円〜300万円程度のまとまった費用がかかる可能性があります。
諸費用ローンは金融機関によって内容や条件が異なりますが、融資額は物件価格の1割以内としているところが多いです。
諸費用ローンで借りたお金については、諸費用に充てるだけでなく、修繕積立金などの負担金や家具や電化製品の購入、引っ越し代金などに充てることも可能です。
自己資金の余裕がない家庭にとって、諸費用ローンは非常に頼もしい存在ですよね。
しかし、自己資金を準備して対応しないと将来的に返済額の負担が大きくなってしまいます。
また、諸費用ローンは確実に借りられると決まっているわけではありません。
住宅ローンと同じように審査があるため、場合によっては審査が通らずローンを利用できない可能性もあります。
特に、住宅ローンの年間返済額と諸費用ローンの年間返済額を合わせた返済負担率を審査で見られるため、住宅ローンを融資可能額ギリギリで借りている場合は審査が通らない恐れがあります。
審査が通ったとしても、住宅ローンの返済額+諸費用ローン返済額を毎月返済しなければならないため、家計に余裕がなくなるかもしれません。
⇒住宅ローンの事前審査と本審査の違いって?審査の流れを徹底解説!
⇒住宅ローンの審査に通らない原因は職業?年収?審査に通るコツとは
⇒夫婦で家を買うならペアローンはおすすめ?収入合算との違いを解説
⇒【プロ解説】住宅ローン一括審査の4大メリット!デメリットはない?
4.家の購入後に支払う費用の詳細
次に、住宅購入後に支払う費用について解説していきます。
- ・不動産取得税(支払いは一度だけ)
- ・固定資産税・都市計画税(年4回)
- ・管理費・修繕積立金(毎月)
4-1.不動産取得税
住宅を建築・購入する際にかかる税金の1つに不動産取得税があります。
「家」と「土地」それぞれにかかります(相続の場合は非課税)。住宅の取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に「納税通知書」が届きます。
土地や家屋を購入した際や、注文住宅を建築して新しく不動産を取得した際は、「不動産取得税」を納めなければなりません。
不動産取得税が必要となるのは、家や土地などの不動産を取得したタイミングであり、入居や引き渡し、登記したタイミングではありません。
税額は、家や土地の「課税標準額(固定資産税評価額)×税率」で算出されます。
税率については原則4%ですが、2027年3月31日までの軽減措置により、現在は土地と住宅は3%となっています。
課税標準額が大きいため、1%の税率の違いでも不動産取得税は大きく変わってきます。
現在、軽減措置により税率が1%低くなっていますが、それ以外にも条件を満たせば不動産取得税を安くすることができます。
4-1-1.土地にかかる不動産取得税
土地のうち宅地については、課税標準額が1/2になる特例が2027年3月31日まで適用されます。
特例を適用した場合の不動産取得税の計算方法を見ていきましょう。
まず、課税標準額を固定資産税評価額の2分の1で計算し、税率3%をかけます。
「固定資産税評価額 × 1/2× 3%=不動産取得税(控除前)」
先ほどの計算に加え、ABいずれかの金額を控除できます。
- ・A……45,000円
- ・B……(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3%
4-1-2.建物にかかる不動産取得税
新築の住宅であれば、床面積が50㎡以上で240㎡以下などの一定の条件を満たせば、課税標準額から1,200万円が控除されます。2026年3月31日までに認定長期優良住宅を取得した場合は、1,300万円が控除されます。
そのため、もし課税標準額が1,200万円以下の場合は不動産取得税は課税されません。
しかし、中古物件の場合は、下記のように新築された時期によって控除額が決まります。
そのため、築年数の古い物件だと新築のように1,200万円もの控除を受けることはできません。
取得した物件が中古住宅の場合は、新築住宅のように1,200万円と控除額が決まっているわけではなく、取得した中古住宅が建築された時期によって控除額が決まります。
| 中古住宅の建築時期 | 控除額 |
|---|---|
| 1976年1月1日〜1981年6月30日 | 控除額350万円 |
| 1981年7月1日〜1985年6月30日 | 控除額420万円 |
| 1985年7月1日〜1989年3月31日 | 控除額450万円 |
| 1989年4月1日〜1997年3月31日 | 控除額1,000万円 |
| 1997年4月1日以降 | 控除額1,200万円 |
家屋の不動産取得税が減額される特例の適用については中古か新築かで大きく異なります。
新築住宅の不動産取得税の場合から具体的に見ていきましょう。
- 不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 1,200万円) × 3%
新築住宅の場合、1,200万円を控除できる特例適用の条件は次のようになっています。
- ・居住用その他も含め住宅全般に適用(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)
- ・課税床面積が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上) 240㎡以下
中古住宅の不動産取得税については次のようになります。
- 不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 控除額) × 3%
控除額は都道府県により異なるため、住所を管轄する自治体へ確認しましょう。
中古住宅の場合、特例適用の条件は次のようになっています。
- ・居住用の住宅に適用(マイホーム・セカンドハウスなど)
- ・課税床面積が50㎡以上 240㎡以下
- ・1982年1月1日以降に新築されたか、一定の耐震基準に適合している
不動産取得税の軽減措置については、手続き方法が都道府県で異なります。
事前に手続き方法や期日などを確認して確実に利用できるようにしましょう。
⇒不動産を取得した時だけに課税される不動産取得税とは?
4-2.固定資産税・都市計画税
一年に一度、固定資産税と都市計画税の課税もありますので、現金はできるだけ残すことをおすすめします。
固定資産税とは、毎年1月1日現在、各市町村の固定資産課税台帳にその土地や家屋の所有者として登録されている人が負担するものです。
都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋には都市計画税も上乗せされます。
マイホーム購入後にかかるお金は、管理費や修繕積立金、駐車場代、メンテナンス費用などだけではありません。
毎年、固定資産税がかかりますし、マイホームを持つ場所によっては都市計画税もかかります。
固定資産税は、自治体にもよりますが、4月・7月・12月・2月など4回に分けて支払うのが一般的です。
4-2-1.固定資産税
固定資産税は、土地や建物、償却資産に対してかかる税金で、税額は「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」で算出可能です(税率は市町村によって異なります)。
固定資産税評価額は、固定資産評価員が評価をして市町村長が価格を決定し、3年ごとに評価替えがされます。
そして、自らの居住用などの住宅用地の場合は、固定資産税の評価額が下記のように軽減されます。
- ・200㎡以下の小規模住宅用地:評価額の1/6
- ・200㎡を超える住宅用地 :評価額の1/3
仮に200㎡を超える住宅用地の場合でも、200㎡までの部分は評価額の1/6で、200㎡を超える部分は床面積の10倍までは評価額の1/3で評価されます。
新築物件の場合、購入から3~7年の間、建物の分の固定資産税が半額になる軽減措置が適用されます。
新築住宅で120㎡までの部分は3年間(構造によっては5年間)固定資産税が1/2になります(2026年3月31日までの新築の場合)。
一般住宅:新築後3年間
3階建以上で耐火構造・準耐火構造住宅:新築後5年間
また、長期優良住宅に認定された住宅の場合は、新築から5年間(マンション等は7年間)税額が1/2に軽減されます。
4-2-2.都市計画税
都市計画税は、都市計画法における市街化区域にある土地や建物に対してかかる税金で、固定資産税と一緒に課税されます(4月・7月・12月・2月など4回)。
税額計算式は、「固定資産税評価額×0.3%(制限税率)」です。
税率は市町村によって異なりますが、課税評価額の0.3%としているところが主流です。
そして、固定資産税同様、住宅用地の場合は評価額が下記のように軽減されます。
- ・200㎡以下の小規模住宅用地:評価額の1/3
- ・200㎡を超える住宅用地 :評価額の2/3
これらの税金がかかることも把握をしておく必要があります。
自治体により税率が変わるため、自治体の窓口や、地元の工務店・不動産屋に問い合わせるなどして税率をチェックしておきましょう。
4-3.マンションにかかる管理費・修繕積立金
マンションを購入する場合にかかる「管理費」や「修繕積立金」について解説します。
管理費・積立金の額は、マンションや専有面積によって異なります。
まず、管理費はマンションの維持管理のために使われるものです。
- ・清掃・点検
- ・設備の交換
- ・管理会社への報酬など
管理費は、駅から近く分譲価格が高いマンションほど高い傾向にあります。
さらに、マイホームとしてマンションを取得した際は、住宅ローン返済とは別に、毎月、修繕積立金を支払うことが一般的です。
修繕積立金とは、マンションの共用部分の修繕工事費用や建物診断、大規模修繕など、20年〜30年と長期にわたる修繕計画をもとに必要な費用を割り出し、マンションの所有者が毎月積立てをしていく費用のことです。
いつまでも安心・安全に暮らせて、資産価値も落ちないように、将来のマンション修理に向けて少しずつ貯めていきます。
マンションの規模やどのような修繕計画を立てているかにもよりますが、毎月の修繕積立金が1〜2万円することも珍しくはありません。
また、修繕積立金とは別に、入居時や数年に1度のタイミングでまとまった費用を積み立てる修繕積立一時金の支払いが必要な場合もあります。
- ・屋上の防水
- ・階段などの底部塗装
- ・外壁の修繕 など
同じマンション内でも、専有面積が大きいほど積立費用も大きくなります。
修繕積立金や修繕積立一時金の規定については、購入するマンションによって異なるため、必ず購入前に確認しましょう。
5.まとめ
家の購入には多くの費用が必要となります。
さらに家や土地は、購入した後にもさまざまな出費があります。
しかし、事前にかかる費用と節約する方法がわかっていれば、最低限の資金でマイホーム購入をすることができるでしょう。
購入する物件について迷っている方は「TERASS」という不動産エージェントでプロからの提案を受けてみるのも一つの手ですよ。